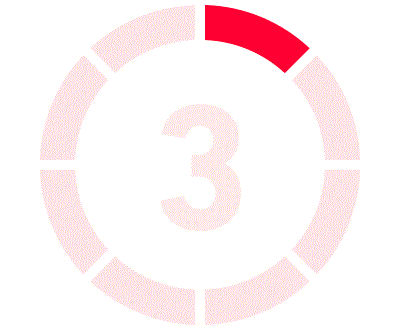
大きな事件が発生すると、フェイクニュース(主にネット上で発信されるウソの情報でつくられたニュースのこと)が出回るケースが増えます。ウソを見分ける方法として、適切でないものはどれでしょう?
- A
一番はじめの発信者は誰かを見極める
- B
国や自治体の公式サイトや、ニュースサイトなど、SNS以外の情報と照らし合わせる
- C
自分に教えてくれた人が正直な人かどうかを考える
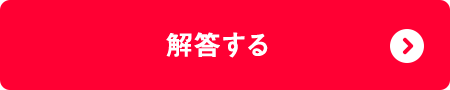
学校内の人間関係に関わる「ネットいじめ」に関する情報として正しいものをすべて選んでください。
- A
SNSに直接悪口を投稿する他に、本人の嫌がる画像などを拡散させることも「ネットいじめ」に含まれる
- B
直接悪口を言われたり危害を加えられるいじめの他に、インターネット上で悪口を書き込まれる「ネットいじめ」に関する相談も学校にすることができる
- C
「ネットいじめ」にあった場合に、児童生徒や保護者は発信された情報の削除や発信者を特定するための協力を、法務局などに求めることができる
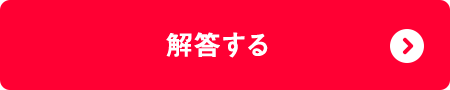
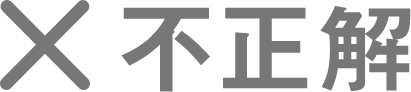
- A
SNSに直接悪口を投稿する他に、本人の嫌がる画像などを拡散させることも「ネットいじめ」に含まれる
- B
直接悪口を言われたり危害を加えられるといったいじめの他に、インターネット上で悪口を書き込まれる「ネットいじめ」に関する相談も学校にすることができる
- C
「ネットいじめ」にあった場合に、児童生徒や保護者は発信された情報の削除や発信者を特定するための協力を、法務局などに求めることができる
2013年に制定された「いじめ防止対策推進法」では、計画的・組織的にいじめ対策を行うことを学校や教育委員会などに義務付けています。児童生徒からいじめについて相談があれば、学校はいじめ対策のための組織をつくることになっており、学校はこの組織でいじめの事実の有無などを調査しなければなりません。いじめには「ネットいじめ」も含まれており、「ネットいじめ」が行われている場合は、児童生徒や保護者が情報開示を求める際に、法務局などへ協力を求めることが可能です。
もし「ネットいじめ」にあった場合は、証拠を残すためにスクリーンショットを撮っておくことが大切です。
量が多い場合はその画面をスクロールしているところの動画を残しておくのもよいでしょう。

次のうち、肖像権の侵害に当てはまる可能性があるものをすべて選んでください。

- A
本人の許可なく寝顔の写真をSNSにアップする
- B
仲の良い友人と一緒に撮った写真を本人の許可なくSNSにアップする
- C
会社や地域、学校のイベントで撮影した顔がわかる写真を本人の許可なくホームページにアップする
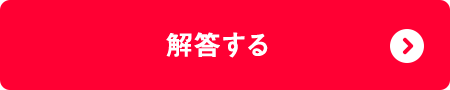
子どもから「身に覚えのないお金を請求するメールが届いた」と相談されました。次のうち、あなたが最初にとるべき行動で間違っているものをすべて選んでください。

- A
子どもを叱って、反省させる
- B
請求のメールの文面をしっかりと確認する
- C
請求されたお金を振り込む
- D
消費生活センターや行政の相談窓口など専門機関に相談する
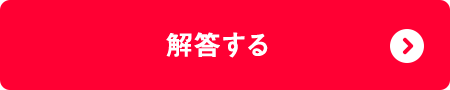
子どもにとって有害なサイトへのアクセスをブロックしてくれる「フィルタリング」の説明について、間違っているものをすべて選んでください。
- A
個別のアプリごとに使用・不使用は設定できない
- B
フィルタリングは一度設定すると変更できない
- C
フリーWi-Fiを使うとフィルタリングが機能しない
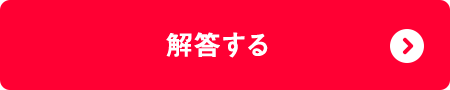
子どもが、実際には会ったことがないSNS上の友達とやりとりをしているようです。子どもに伝えておくべきこととして、当てはまるものをすべて選んでください。

- A
写真や動画は、もし拡散されたら完全には消せないため、絶対に相手へ送らない
- B
保護者への相談なくSNSで知り合った友達に会いにいかない
- C
住んでいる地域や学校名など、個人情報につながることは教えない
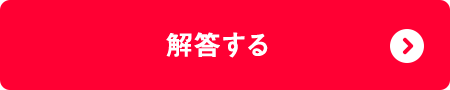
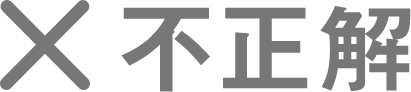
- A
写真や動画は、もし拡散されたら完全には消せないため、絶対に相手へ送らない
- B
保護者への相談なくSNSで知り合った友達に会いにいかない
- C
住んでいる地域や学校名など、個人情報につながることは教えない
ネットを介したやりとりには、楽しみだけでなく危険が潜んでおり、最近では、誘拐事件や命にかかわるような凄惨な事件も起きています。
警察庁の「令和3年の犯罪情勢」調査によると、SNSに起因する事犯の被害児童数は令和3年の1812人に引き続き、令和4年も1732人と高い水準にあることがわかりました。
また、SNS等が起因となり、性犯罪等の被害に遭う18歳未満の人も増えています。子どもを家出させ自分の支配下に置く行為は、たとえ子どもが望んだことだとしても未成年者誘拐罪に当たる場合があります。子どもの下着姿や裸の写真を撮って送らせることは、児童ポルノ製造罪に当たる場合があります。保護者に無断で深夜に子どもを連れ出すことは、ほとんどの地域で条例違反になります。こうした法的な事柄も含め、日頃からお子さまとSNS利用のリスクについて話し合っておくとよいでしょう。
出典:警察庁ウェブサイト

世界中で人気のサービスに「Instagram」や「TikTok」があります。これらのサービスには年齢制限があります。
利用していいのは何歳からでしょうか。正しいものを選んでください。
- A
5歳以上
- B
10歳以上
- C
13歳以上
- D
18歳以上
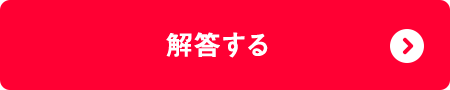
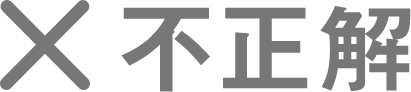
13歳以上
「Instagram」や「TikTok」等、多くのサービスが利用年齢を13歳以上と規定しています。しかし、東京都(都民安全推進本部)の調査によると、約4割の保護者が「Instagram」、「TikTok」、「X(旧Twitter)」、「Facebook」等、一部のSNSに利用規約上、年齢制限があることを知りませんでした。(※)
犯罪被害を防ぐためにも、家族でSNSの年齢制限についてあらためて確認しましょう。
※出典:「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査」(東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部)
ちなみに、「LINE」の利用推奨年齢は12歳以上です。

自分の子どもが芸能人のSNSに「気持ち悪い」「芸能界から消してやる」と書き込んでしまいました。この場合、どのようなリスクがあるでしょうか。当てはまるものをすべて選んでください。

- A
犯罪になる可能性がある
- B
民事訴訟で慰謝料などを求められる可能性がある
- C
個人的な感想なので何の問題もない
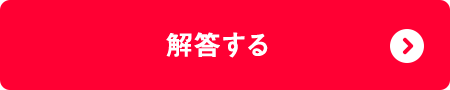
子どもから「学校の仲の良い友達の間でグループラインをつくることになった。自分も参加したいからLINEのフィルタリングを外してほしい」と言われました。親子でよく話し合ったうえでLINEの使用を許可する場合、フィルタリングについてあなたが取るべき行動で正しいものは次のうちどれでしょう?

- A
フィルタリングサービスは一度加入すると解除できない
- B
フィルタリングを一律解除する
- C
アプリを個別にカスタマイズしてLINEの使用を許可する
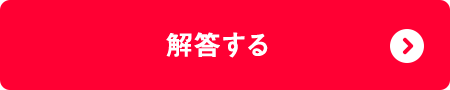
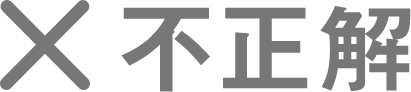
アプリを個別にカスタマイズして
LINEの使用を許可する
まず、どうしてLINEを使いたいのかを子どもと話し合い、LINEを使用する場合の注意点(悪口を書き込まない、仲間外れをしないなど)を子どもに確認してから使用させるかどうかを決めることが前提です。そのうえで、フィルタリングを一律解除するのではなく、アプリのカスタマイズで個別に設定できるので、LINEのみ使用できるようにしましょう。
ちなみに現状ではフィルタリングを設定していない、または子どもにとって何らかの不便があったためにフィルタリングを解除したという親が多数いることがわかっています。
フィルタリングは、LINEに限らず、特定のサービスやアプリのみ使えるようにカスタマイズできるので、有効に活用しましょう。

子どもから「掲示板に自分の悪口が書き込まれているのを見て嫌な気持ちになった」という報告を受けました。確認してみると子どもについての中傷が個人情報と共に書き込まれています。誹謗中傷を書き込まれたときの対応について、間違っている行動を選んでください。

- A
反撃をする
- B
スクリーンショットを撮っておく
- C
プロバイダーに通報する
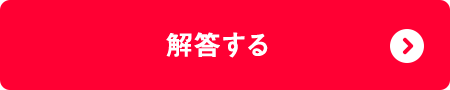
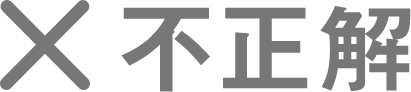
反撃をする
困ったときは一人で抱え込まずに、誰かに相談することが大切です。
まずはプロバイダーの該当窓口に相談しましょう。削除・対応してくれない場合は公的機関に問い合わせを行います。
誹謗中傷の内容が度を越していたり、炎上しているなど、場合によっては「犯罪」ととらえ、警察に相談が必要な場合もあります。
また、総務省が事業支援している「違法・有害情報相談センター※」では、誹謗中傷の書き込みや無断で個人情報をさらされた場合などの相談をインターネットで受けつけています(※上記センター名で検索)。
問い合わせ前に、証拠として誹謗中傷が書き込まれている部分のスクリーンショットを撮影しておくことが大切です。
21年4月に「改正プロバイダ責任制限法」という法律が成立し、22年10月から施行されました。これにより誹謗中傷を行った人を特定するための開示手続きが、数カ月から半年ですむようになりました。また、裁判所は、事業者に誹謗中傷を行った人の情報を消さないよう、命令を出すことも可能になりました。

ニュースで子どもの高額課金についてのトラブルについて知りました。子どもに高額課金させないためにとるべき行動として間違っているものは以下のどれでしょう?
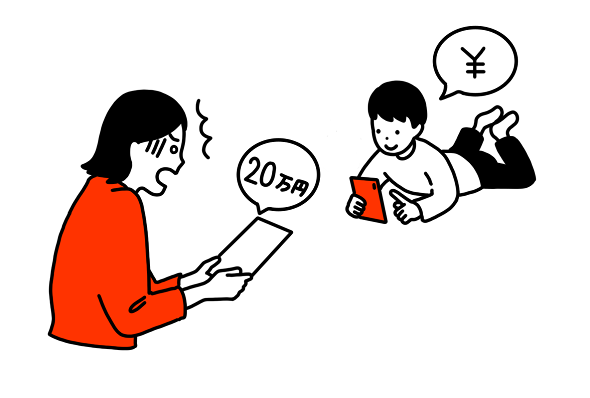
- A
スマートフォンの課金利用制限を設定する
- B
課金ルールについて話し合う
- C
親のクレジットカードを子どもの手の届かないところで厳重に管理する
- D
ダウンロード無料のアプリのみ利用を許可する
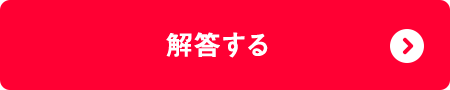
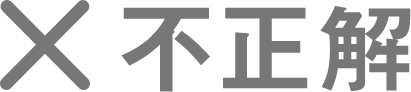
ダウンロード無料の
アプリのみ利用を許可する
あらかじめ子どもと話し合って課金についてのルールを決めておくことが大切ですが、子どもは夢中になればなるほどリミッターが外れてつい課金してしまいがちです。利用制限を設定しておけば、使い過ぎを確実に予防することができます。
ダウンロードは無料でも、ダウンロード後に課金できるアプリもあるので、決済できないようにフィルタリングをかけるなど制限機能を設定しておくことが大切です。
未成年者が保護者の承諾なくオンラインゲームの課金をしてしまった場合は未成年者契約の取消しが可能な場合があります。ただし、子どもが課金したと証明することが難しく適応にならないことも多いため、課金自体を未然に防ぐ対策を行っておきましょう。

アカウント乗っ取り被害にあわないための予防法として、正しいものをすべて選んでください。

- A
サイトごとにIDやパスワードを変える
- B
二段階認証を設定する
- C
生体認証を使用する
- D
パスワードを忘れないように、同じパスワードを使い回す
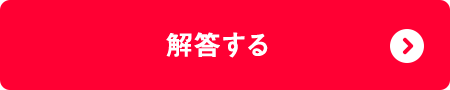
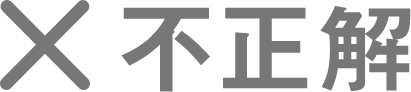
- A
サイトごとにIDやパスワードを変える
- B
二段階認証を設定する
- C
生体認証を使用する
アカウントの乗っ取りとは、悪意を持つ第三者が、勝手に自分のアカウントにログインしてしまうこと。乗っ取られてしまうと、身に覚えのない投稿がSNSにアップされたり、SNSでつながっている家族や友人にメッセージが送られ、個人情報を抜き取られたり、悪質なサイトに誘導されるなどの被害が拡大する恐れがあります。
予防するためには、まず、パスワードの使い回しをやめること。安心なのは、ログイン時の手間を惜しまずに二段階認証を設定する方法。外部の端末から第三者が勝手にログインできないようにすることが重要です。二段階認証がないサービスの場合は、できるだけ複雑なパスワードを設定したうえで、そのパスワードをメモアプリに書き込んでおき、アプリ自体にロックをかけるようにしましょう。

子どものスマホの使い過ぎが気になりました。使い過ぎが気になったときに取るべき方法として、利用できる機能を選んでください。
- A
フィルタリングアプリなどを使って、使用時間を設定できる機能
- B
フィルタリングアプリなどを使って、使用できるアプリを個別に設定する機能
- C
あとから使用時間を確認できる機能
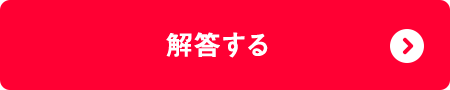
ある日、 スマートフォンの通知を見ると「お客様宛にお荷物のお届けにあがりましたが不在のため持ち帰りました。下記URLよりご確認ください」という身に覚えのない宅配業者を装ったSMS(ショートメール)が届きました。
このURLにアクセスをすると、次のうちどんな事態が予想されるでしょうか?正しいものをすべて選んでください。

- A
宅配業者を装った詐欺の可能性があり、アクセスすると、フィッシング詐欺に遭う
- B
不正アプリをダウンロードさせるページに誘導される
- C
個人情報を入力するよう誘導され、スマホ決済を不正利用され、事件に巻き込まれる
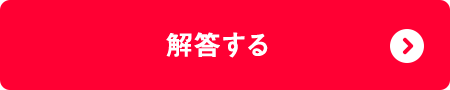
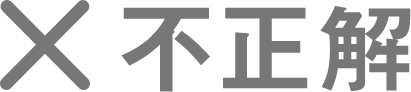
- A
宅配業者を装った詐欺の可能性があり、アクセスすると、フィッシング詐欺に遭う
- B
不正アプリをダウンロードさせるページに誘導される
- C
個人情報を入力するよう誘導され、スマホ決済を不正利用され、事件に巻き込まれる
宅配便通知を装ったSMSを送り付けて詐欺サイトに誘導する下記のような事例(フィッシング詐欺)が確認されています。
・不正アプリをダウンロードさせられて、直後は何も起こらなかったが数日後、見知らぬ人からの着信が止まらなくなり、自分の電話番号から偽SMSが100回以上大量に発信されてしまっていた。
・リンク先のフィッシングサイトで個人情報を入力するよう誘導され、不正に数万円のキャリア決済をされた。
このような恐れがあるので、不審なSMSのURLには絶対にアクセスしてはいけません。

結果を見る前に
アンケートにご協力ください。
アンケートに入力いただいた情報は統計のみに使用し、
それ以外の目的で使用することはありません。
フェイクニュースには誹謗・中傷を目的とした個人発信の投稿などを含む場合もあります。正直な人でもフェイクニュースを信じて拡散してしまうケースも多いです。
虚偽の情報であるフェイクニュースがSNS上で流れ、その情報によって業務が妨害されたり混乱が生じたりすることがあります。
また、近年は、急速に利用が広まる「生成AI」と呼ばれるテクノロジーで本物そっくりな画像・動画も簡単に作れるようになり、真偽の見極めが難しくなっています。
自分に教えてくれた人が誰であっても慌てて情報を拡散したりせず、落ち着いて情報の真偽を確かめる態度が求められます。「大変だ、みんなに知らせなきゃ」と思ったときほど落ち着いて周りの大人に相談するよう、お子さまにアドバイスをお願いします。