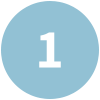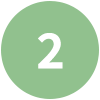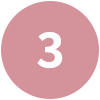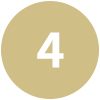当初、2022年10月から予定されていた「アルコール検知器による酒気帯び確認」は、アルコールチェック機器の供給が間に合わないことから当分の間延期されていました。
2023年12月1日から正式に義務化されるため、それまでにアルコール検知器の手配や点呼記録を管理する仕組みを整えるなど、法令に基づいた十分な対策が求められます。

- 参考:内閣府令 内閣府令第六十二号
アルコールチェック義務化における4つのポイント
2023年12月に施行されるのは、道路交通法施行規則第9条の10「安全運転管理者の業務」です。
安全運転管理者の業務が変更(6項と7項の新設)されます。
2022年4月から
運転業務の前後に酒気帯び確認
安全運転管理者に対して、運転者のアルコールチェック(酒気帯びの有無)を目視などで確認することが義務付けられました。
2022年4月から
測定記録の1年間保存の義務化
アルコールチェック(酒気帯びの有無)を行った安全運転管理者は、その記録を作成して1年間保存する必要があります。
2023年12月から
アルコール検知器を使った酒気帯び確認義務化
目視などによる確認に加えて、アルコール検知器を用いたアルコールチェック(酒気帯びの有無)を実施することが義務付けされます。
2023年12月から
アルコール検知器を常時有効に保持
アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持することが義務付けされます。
- 参考:電子政府の総合窓口(e-Gov)道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)
アルコールチェッカー(アルコール検知器)の選び方
アルコールチェッカーは、機器により内蔵されているセンサーや測定方法、測定結果の記録方法などに違いがあります。
アルコールチェッカーの運用方法によって選定する必要があります。
アルコールチェッカーは半導体式がおススメ!
アルコールチェッカーには半導体式と電気化学式の2つの方式がありますが、直行直帰や多くの検知器を必要とする場合は、半導体式をおススメします。
半導体式は小型で軽量なため、持ち運びや取り扱いが簡単です。また、電気化学式に比べてコストが低く、測定時間も短くて利便性が高い特長があります。「ドライバーに1人1台アルコールチェッカーを持たせたい」というニーズに対応することができます。
ただし、企業ごとに重視する条件が異なるため、半導体式を含めた各方式の特長を考慮し、自社の重視する条件全般に合わせて製品選びをすることが大切なポイントとなります。
アルコールチェックを管理する場合はスマホ連携できるものがおススメ!
外出先からの検査結果を管理する際には、スマートフォンと連携可能連携できるものがおススメです。専用のアプリケーションとアルコールチェッカーを連動させることで、スマートフォンから測定結果を一括管理できるので、複数拠点のデータ管理がスムーズになります。さらに、PCへの検査結果データ転送も可能なため、長期間のデータ保存にも便利です。検査結果のデータをクラウド上で管理することで、点呼記録を手作業で管理する必要がなく、データ保管も容易になります。管理者の業務効率化にも貢献します。
外出先で酒気帯び有無の確認・点呼ができる
おススメ業務用アルコールチェッカー(アルコール検知器)
スマートフォンと連携するアルコールチェッカーなら検知結果を管理者に通知してくれるので、
ドライバーや管理者の負担が少なくなります。
直行・直帰ができるため、点呼業務の省力化や時間短縮につながります。
小型で持ち運びしやすいアルコールチェッカー
持ち運びに優れた携帯式アルコールチェッカーです。直接息を吹きつける方式で簡単に測定することができます。運行管理サービス「スマートフリート」と連携することでアルコールチェック義務化にも簡単に対応できます。
<運行管理サービス スマートフリートと連携した場合>
- 携帯式のアルコール検知器で場所を選ばずアルコールチェック可能
- アルコールチェックした情報はリアルタイムでクラウドに保存。法令対応として1年間のデータ保存をサポート
- 顔認証でなりすまし防止
- 車両運行管理付きで業務効率化