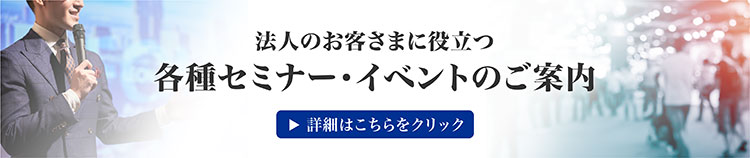フォーム読み込み中
ニューノーマル時代を迎えて、人々の働き方や暮らし方は大きく変化しました。以前はオフィスに出社して働くことが当たり前でしたが、多くの企業でテレワークが推進され、時間と場所にとらわれない働き方が一般的になりました。
テレワーク導入のメリットを感じるシーンがある一方で、新たな課題も浮き彫りにされつつあります。例えば、従業員間のコミュニケーション不足により仕事がスムーズに進まない、信頼関係の構築が難しいと悩んでいる人は少なくありません。社会の変化は、働く環境はもちろん、人材教育のあり方や従業員のメンタル面にも大きく影響を与えています。
特に部下を管理・指導し、ケアしていく立場のマネジメント層(中間管理職)の育成は、大きな課題です。また、負担が増えるのに伴い、マネジメント層自身へのケアの重要性も認識されるようになりました。今回は、ニューノーマル時代における企業活動の変化、新たに必要とされるようになったスキルやマネジメント面の対応を確認しながら、マネジメント層への教育とケアについて考えてみましょう。
企業活動は“非接触”が前提に
新型コロナウイルス感染症の流行以降の社会では、あらゆるシーンで、感染を予防するために人と人との接触を極力避ける新しい生活様式が求められるようになりました。もちろん企業活動でも、非接触が前提条件になりつつあります。
流行の初期には、中小企業を中心に、ネットワーク環境やセキュリティ面の不備などが原因でなかなかニューノーマルへの対応が進まない企業も多く見られました。しかしその後、新型コロナウイルス感染症の流行が長引くなかで、多くの企業において時間と場所にとらわれないオンラインを活用した働き方や人材育成を積極的に取り入れようとする動きが加速されています。今後は企業規模にかかわらず、多くの企業がテレワークをはじめとした自由度の高い働き方へ対応した環境を整えていくと考えられます。
テレワークのメリット・デメリット
ニューノーマル時代の働き方として主流となるテレワークには、さまざまなメリットがある一方で、デメリットも存在します。ニューノーマル時代の企業活動における課題を把握するために、テレワークのメリットとデメリットを整理しておきましょう。
・メリット
テレワークを導入すると、通勤・移動にかかる時間が削減されます。また、テレワークと同時にオンラインで使えるコミュニケーションツールを導入した場合、よりスムーズに情報共有できるようになります。その結果、業務の効率化が進み、生産性が高まることが期待できます。従業員にとっても、より仕事に集中できるようになる、移動時間が短縮されてプライベートの時間が増えるといったメリットにつながります。
また、全ての従業員が毎日出社しなくてもよい場合、ワークスペースを最小限にできるため、オフィスのスペースを縮小することで賃料を削減することができます。賃料のほか、机や椅子などの設備費、光熱費、紙や印刷費といったコストも削減されます。なかには、本格的なテレワークの導入後、コストカットや地域活性化、地方からの優秀な人材確保など、さまざまなねらいから本社機能の一部を賃料の安い地方に移動させる企業もあります。
ニューノーマル時代以前から高まっていた多様な働き方へのニーズに対応しやすくなることも、大きなメリットと言えます。テレワークを導入すれば、地方も視野に入れて、住んでいる場所に関係なく有能な人材を雇えるようになる上、従来は育児や介護のために離職を余儀なくされていた人を雇用し続けることができるため、人材の確保につながります。
さらに、BCP(事業継続計画)の観点からも、テレワーク導入には意義があります。テレワーク体制が整っていれば、感染症の流行や災害といった事態においても事業を継続できるため、業績へのダメージを最小限に抑えることができるのです。
・デメリット
最も懸念されるのが、情報漏えいのリスクです。テレワーク中の従業員は、自宅のほかに、カフェや図書館、コワーキングスペースといった公共の場で仕事をすることもあり得ます。そのような場所に設置されている無料Wi-Fiを使用することで、その通信内容から機密情報が流出する危険性があります。地味ではありますが、画面を覗き見されることによる情報漏えいのリスクもあるのです。また、社用のノートPCやタブレット端末の紛失・盗難リスクもあります。
社内コミュニケーションが不足しやすいのも、テレワークのデメリットと言えます。オフィスにいれば周囲にいる上司や同僚にささいな疑問や業務上の悩みを相談する機会がありますが、テレワークの場合はそうした気軽なコミュニケーションが難しいため、従業員が業務内容を完全に理解できない場合や、課題がスムーズに解決できない場合もあり得ます。人によっては孤独を感じやすくなり、ストレスでモチベーションを維持しづらくなるかもしれません。複数の従業員の生産効率が落ちた結果、チームや部署全体の生産性の低下につながる場合もあるでしょう。
さらには、その状態が長期的に続けば、有能な人材の離職につながる可能性も考えられます。また、マネジメント層にとっては、部下が働く姿が直接見えるわけではないため、勤怠管理や進捗管理、指導育成、評価などに工夫が求められる点も大きな課題です。
・デメリットへの対策
最も懸念されるのが、情報漏えいのリスクです。テレワーク中の従業員は、自宅のほかに、カフェや図書館、コワーキングスペースといった公共の場で仕事をすることもあり得ます。そのような場所に設置されている無料Wi-Fiを使用することで、その通信内容から機密情報が流出する危険性があります。地味ではありますが、画面を覗き見されることによる情報漏えいのリスクもあるのです。また、社用のノートPCやタブレット端末の紛失・盗難リスクもあります。
社内コミュニケーションが不足しやすいのも、テレワークのデメリットと言えます。オフィスにいれば周囲にいる上司や同僚にささいな疑問や業務上の悩みを相談する機会がありますが、テレワークの場合はそうした気軽なコミュニケーションが難しいため、従業員が業務内容を完全に理解できない場合や、課題がスムーズに解決できない場合もあり得ます。人によっては孤独を感じやすくなり、ストレスでモチベーションを維持しづらくなるかもしれません。複数の従業員の生産効率が落ちた結果、チームや部署全体の生産性の低下につながる場合もあるでしょう。
さらには、その状態が長期的に続けば、有能な人材の離職につながる可能性も考えられます。また、マネジメント層にとっては、部下が働く姿が直接見えるわけではないため、勤怠管理や進捗管理、指導育成、評価などに工夫が求められる点も大きな課題です。
ニューノーマル時代に適した人材育成方法
ニューノーマル時代においては、働き方はもちろん、人材教育のやり方にも見直しが必要です。また、前述したコミュニケーション不足や勤怠・進捗管理の難しさから、マネジメント力がこれまで以上に重視されます。マネジメント層の負担を軽減するためにも、新たな形を模索・検討して、人材育成を効率化していきましょう。具体的には、次のような取り組みが考えられます。
・業務マニュアルを作成し、デジタル化する
まず着手したいのが、業務内容と新しい体制に合わせた業務マニュアルの作成です。分かりやすく完成度の高い業務マニュアルがあれば、従業員の教育にかかる負担を軽減し、業務の効率化、標準化を図ることができます。完成したマニュアルはデータにしてオンラインでの管理・共有を徹底し、業務に関係する従業員がいつでも確認できるようにしておきましょう。
・オンライン教育を導入する
これまで従業員教育のために集合研修を実施していた企業の多くは、新しい生活様式に対応するため、録画された講義を従業員が自分のペースで受講できるeラーニングや、Web会議システムを活用してライブ形式で実施する研修といった、オンラインでの教育方法に切り替えはじめています。それによって、マネジメント層が部下を直接指導・教育するのにかかる労力を大幅に減らせるというメリットもあります。
また、eラーニングを導入する場合、LMS(学習管理システム)を使って受講者のスケジュールや学習状況、成績などを管理することができるため、教育の進捗管理という面においてもマネジメント層の負荷を削減でき、効率化が進みます。もちろんeラーニングやオンライン研修は、マネジメント層自身への教育にも有効な手段です。
動画共有サービスを利用してeラーニングを導入することも一つの方法です。その場合、セキュリティ面の配慮も必要です。ユーザ設定や動画ごとのアクセス制御、動画視聴ログなどの機能がある動画共有サービスを利用するとよいでしょう。
法人向け動画共有サービス「MOVIE LIBRARY」 サービス紹介資料
法人向け動画共有サービス「MOVIE LIBRARY」導入事例
ニューノーマル時代に必要とされるスキル
テレワークやオンライン会議が日常化した職場では、業務の進め方がこれまでとは大きく違ってきます。従業員一人一人に見合ったスキルが求められるようになります。次に、ニューノーマル時代のビジネスパーソンに必要とされるスキルと、その理由を紹介します。
・自発性
従来の日本企業では、働く時間で従業員を評価する傾向がありました。一般的に、長い時間働けば頑張っていると見なされ、高く評価されたり、残業代が加算されて収入が上がったりしていたのです。また、毎日きちんと出社して上司に指示された通りに業務を進めるという、真面目ではあるものの受け身な姿勢の従業員も少なくなかったはずです。 しかし、テレワーク下では従業員の労働時間を明確に把握することは難しくなるため、今後は多くの企業が成果に重点を置いた評価方法に移行していくと考えられています。成果主義が進めば、従業員には自らアイデアを出したり、業務の改善策を提案して率先して進めたりといった自発的な働き方が求められるようになります。意欲的に学び、成長しようとする姿勢も重視されるでしょう。当然ながらマネジメント層には、部下の自発性を認め、促し、適切に評価するスキルが求められます。
・自己管理能力
テレワーク下では、従業員は時間や場所に縛られずに働ける上、ある程度、自分のペースで業務を進めることができるようになります。ただ、その分、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。他の従業員の視線や雑談などのコミュニケーションが不足したなかでも、モチベーションを保ちながら期日に間に合うように業務を進めなければなりません。そのため、ニューノーマル時代のビジネスパーソンには、自己管理能力や計画性が求められます。マネジメント層には、自分自身の業務を管理しながら、部下の業務の進捗や仕事量、モチベーションも適切に管理していくという高度なマネジメント能力が必要とされます。
・オンラインでのコミュニケーション能力
テレワークでは、社内・社外にかかわらず、人とのコミュニケーションをオンラインで行う機会が大幅に増えることが予想されます。Web会議では、対面でのコミュニケーションに比べるとその場の空気や相手の反応が分かりにくいため、より明瞭に、気持ちを込めて話さなければなりません。もちろん、伝えるスキルだけでなく、相手から言葉を引き出し、真意を確認する会話力も今まで以上に重要になります。要件の連絡や報告にメールやチャットを使うことが多くなるので、論理的で分かりやすい文章を書くスキルも必要です。
特にマネジメント層は、部下への指示の出し方に注意しなければなりません。従来のオフィス勤務では、一度部下に指示を出したあと、質問を受けてあらためて説明し直したり、顔を合わせた際に確認したりといった対応が可能でした。しかしテレワーク中心の組織では、部下と頻繁に顔を合わせることができないため、途中での軌道修正が難しくなります。曖昧な指示を出すことで、対応にかかる時間が長くなることもあります。チャットやメールでも一度で部下に理解してもらえるよう、具体的かつ明確な指示を出すスキルが必要になります。
前述の通り、テレワークには従業員どうしのコミュニケーションが不足しやすいというデメリットがあります。だからこそ職種、部門にかかわらず、テレワークを行う従業員全てが意識的にコミュニケーションスキルを高めていく必要があるのです。リモート状態で働く部下たちを管理しなければならないマネジメント層には、相手の立場や状況に合わせたより柔軟なコミュニケーションが求められます。
・デジタル端末・ツールを使いこなす力
テレワークが本格始動すれば、使用するデジタル端末やツールの数が増えることが予想されます。ニューノーマル時代の企業の従業員は、日常の業務のなかでスムーズに使いこなしていくために、それらの端末やツールの利用方法を早めに習得しておく必要があります。マネジメント層は、端末やツールの利用方法が分からない部下を指導できるよう、一般の従業員以上に利用方法に精通していなければなりません。また、新しいツールを業務管理や社内コミュニケーションの活性化に生かすというマネジメント層ならではの視点も求められます。
・セキュリティ意識
セキュリティ面のリスクは、テレワークの最大のデメリットです。前述のように、テレワーク下では、公共の場で無料Wi-Fiを使って仕事をすることによる不正アクセスや情報漏えい、端末の盗難、紛失など、さまざまなリスクがあります。企業側が環境を整えて対策することは必須ですが、マネジメント層はもちろん、従業員一人一人にセキュリティ意識が求められます。従業員がセキュリティ対策のための知識やスキルを身につけるためには、研修で教育を受ける機会が不可欠です。
ニューノーマル時代に求められる組織マネージメント
ただし、従業員が上記のスキルを備えただけでは、テレワークを進める上での課題は解決されません。テレワークで生産性が低下する場合、最も大きな要因として考えられるのが、マネジメントがうまく機能していない可能性です。マネジメントのやり方次第で、テレワークは生産性を高めるきっかけにも、逆に低下させる要因にもなり得るのです。
ニューノーマル時代においては、従業員一人一人のスキルを高めるとともに、組織マネジメントのやり方も変革していかなければなりません。では、どのようなマネジメントが求められるのでしょうか。ここからは、テレワークの推進にあわせてマネジメント層が実際に行うべき対応・施策を詳しく見ていきましょう。
・タスク・進捗状況を見える化する
テレワークを導入した企業のマネジメント層の多くが直面するのが、「部下が何をしているのか、どんな風に働いているのか分からない」という悩みです。オフィスで一緒に働いていると、仕事ぶりや業務の進み具合、忙しさを自然に把握することができます。しかし、テレワーク中はそうはいきません。
上司が部下の業務の進捗をうまく把握できなければ、適切なタイミングで指示やアドバイスをすることができなくなるため、業務がうまく進まなくなり、生産性が低下しかねません。また、部下が課題を抱えていることやオーバーワーク状態になっていることに気が付けないケースもあります。
トラブルを防いで適切に業務管理を行うためには、リモート状態でも従業員それぞれのタスクや進捗状況を把握できる仕組みを作る必要があります。タスクをオンライン上で分かりやすく見える化して、従業員どうしで共有、管理できるタスク管理ツールを活用するのもひとつの方法です。「LINE WORKS」のようなコミュニケーションツールを活用して、決まったタイミングでチャットによる業務報告を義務づけるのもいいでしょう。
ただし、上司からあまりに頻回の報告を求めると、部下の負担になる可能性もあるので注意が必要です。部下が短時間で入力できて、管理しやすいフォーマットを設定し、適度なタイミングで報告してもらうようにしましょう。なお、管理職が複数のエリアを管轄している場合は、リモート状態でも進捗状況を確認できるようになることで、これまで拠点間の移動にかけていた時間を短縮できるというメリットもあります。
・コミュニケーションを増やす
テレワーク中心の働き方になると、オフィスに通勤していた時代には当たり前だった移動時間や仕事の合間の雑談、飲み会での交流といった日常的なちょっとしたコミュニケーションができなくなります。オンラインツールがあれば、スムーズに情報共有を行うことはできますが、それだけで部下の人となりを知り、成長をフォローするのは至難の業です。マネジメント層には、意識的に部下とのコミュニケーションの機会を増やしていく努力が求められます。
そこでぜひ実施したいのが、Web会議ツールを活用した定期的な1on1ミーティングです。1on1とは、上司と部下が一対一で行う面談のことで、ニューノーマル時代以前から、新しい人材育成手法として注目されていました。上司との面談というと評価面談を思い浮かべがちですが、1on1は、評価や業務管理のために行われるものではありません。部下の成長とスキルアップを目的としていて、部下が現状や業務を進める上で直面している悩みについて上司と話し合い、気づきを得たり助言を受けたりするために行われます。頻度は、1週間に一度、1ヵ月に一度といった比較的短いサイクルで行われるのが一般的です。1on1の回数を増やすと、テレワーク下でも部下の状況を把握し、業務上の課題を共有してフォローすることができます。
1on1は上司と部下が一対一でコミュニケーションを図る手段ですが、部下どうしのコミュニケーションの機会をつくるのも、マネジメント層の役割と言えます。同じ部署やグループのメンバーどうしが親睦を深められるような場づくりも必要でしょう。具体的な施策としては、互いにあまり接点のない2人の部下にWeb会議に参加してもらい意見を聞く、オンラインでのランチ会や飲み会を開催する、チャットツールや社内SNSなどで雑談用のスペースを作る、といったものが考えられます。
・部下のモチベーションの維持、向上を図る
テレワーク中のマネジメントには、前述のように、タスクの見える化や業務報告のルール化、1on1といった対応が必要になります。しかし、これらの対応は、やり方次第では、部下に「上司から監視されている」という感覚を覚えさせる懸念があります。従業員の働く環境やワーク・ライフ・バランスの改善につながるはずのテレワークが、かえって従業員の負担やストレスを増大させかねません。
ニューノーマル時代のマネジメント層には、部下を監視せずにモチベーションを維持させていくという高度なマネジメントが必要とされます。管理職は「部下を監視し、管理する」という従来の感覚から脱却して、「部下の能力を引き出し、育成する」という観点で業務にあたらなければなりません。
人材育成の基本は、部下の現在の状況やスキルを適確に把握し、能力に見合った業務を与えて適切にフォローしていくことです。そのためには、部下と地道に対話を重ね、十分な信頼関係を築く必要があります。信頼関係に基づくマネジメントが実現できれば、テレワーク下でも従業員はモチベーションを維持し、成長し続けることができるでしょう。
・目標を設定し、共有する
従業員のモチベーションを維持するためには、目標設定も重要です。オフィスで働いていると、日々の会話や雑談を通して、上司や同じチームのメンバーと目標を共有できる場面があるものですが、テレワーク下では、自分が何のために、何を目指して働いているのか分からなくなりがちです。これまで以上に、組織全体やチームの目標・ビジョンを明確にして部下に伝えていかなければなりません。
従来、企業が目標を管理する際の指標として一般的に使われてきたのが「KPI(重要業績評価指標)」や「KGI(重要目標達成指標)」ですが、働き方改革の推進やニューノーマル時代の到来とともに「OKR」という新しい目標管理の考え方が注目を集めています。OKRは「Objectives and Key Results」の略で、「目標と主要な結果」という意味です。
OKRでは、四半期ごとにひとつの目標(O)を定め、その達成に必要とされる複数の動きを、主要結果(KR)として設定します。KPIやKGIが計測可能な数値で表されるのに対し、OKRの場合、Oは計測できない定性的なもの、KRは計測可能な指標にするのがルールです。
OKRには、企業全体の目標と、チーム・個人の目標を連動させやすいという特徴があります。全従業員が同じ方向に向かって業務を進められるため一体感を得やすく、企業目標に対する個人の貢献度が分かりやすいため、従業員はモチベーションを維持しやすくなります。OKRの活用は、ニューノーマル時代の組織マネジメントにおける選択肢のひとつでしょう。例えば、ニューノーマル時代に注目が高まっているメルカリでは、2015年からOKRを導入しています。メルカリでは、会社(グループ全体)の使命(ミッション)として、「新たな価値を生み出す世界的なマーケットプレイスを創る」「信用を創造してなめらかな世界を創る」「次のメルカリ級の事業を作る」の3つを設定しています。そして、価値(バリュー)には「大きな挑戦をする」「1つの課題に全員が全力で取り組む」「プロとして責任をもって仕事をする」を掲げています。これらがつながるようにOKRを設定しているのです。
さらにOKRを運用するにあたり、「グループ全体」「各事業部」「各部署」「各チーム」「個人」の順番にそれぞれのOKRを設定し、グループ全体のOKRが個人レベルまで共有されるような構造になっています。
マネージメント層へのメンタルケアの必要性
ニューノーマル時代の働き方に移行する中で、マネジメント層には重圧がのしかかっています。現代のマネジメント層には、自分自身が現場で売り上げにも貢献しながら部下を指導する管理職としての役割も兼ねたプレーイングマネージャが多く、その負担は相当なものです。
最近ではメディアでも、ニューノーマル時代を生きるストレスフルなマネジメント層へのケアの必要性が問われています。まずは、マネジメント層がマネジメントに集中できるよう、それ以外のルーチンワークを他の従業員に割り振る、RPAやAIといった最新のテクノロジーを積極的に導入して業務の自動化、効率化を図るといった方法で、物理的な負担を軽減する対策が必要でしょう。
それと同時に、社内に産業医やカウンセラーを常駐させる、マネジメント層がその上司に相談できる機会を設けるなど、マネジメント層の精神面をケアできる環境整備を進めることも必要です。マネジメント層自身も、完璧な上司を目指すのではなく、自らに課したハードルを下げ、部下に任せられる仕事は思い切って部下に任せ、精神的な重圧を軽減する工夫をしていくといいでしょう。
ニューノーマル時代の企業運営の要となるマネージメント層に、十分な教育とケアを
テレワークが日常化するニューノーマル時代のマネジメント層は、離れた場所にいる部下たちとオンラインでコミュニケーションを取り合って効率的に業務を管理しながら、部下のモチベーションを高め、成長を促していかねばなりません。それには、前述のスキルはもちろん、総合的で奥行きのある人間力が求められます。
加えて、マネジメント層は、本稿で紹介したオンラインツールを使ったタスクの見える化、1on1による部下の成長促進、OKRを活用した目標管理といった新しい時代の組織マネジメントのノウハウをインプットし続けていく必要があります。もちろん、部下からの質問や相談にスムーズに答えられるよう、最新テクノロジーやツールの使い方、セキュリティ対策など、現場の業務に必要な基礎知識も万全に備えておくといいでしょう。
企業がニューノーマル時代にスムーズに対応できるか否かは、マネジメント層の活躍にかかっていると言えます。しかしその一方で、現場でもプレーヤーとして実力を発揮し、かつ、管理職としての役割も果たせる頼りになる上司像を求められることで、マネジメント層は過剰なストレスにさらされています。
企業側はeラーニングシステムやオンライン研修も活用しながら、マネジメント層が知識やスキルを身につける機会を十分に提供するとともに、産業医やカウンセラーに相談しやすい体制を整えて、精神面のケアもしていかなければなりません。社会全体でニューノーマルへの対応が本格的に進みつつある今、あらためてマネジメント層への教育とケアの重要性を確認しておきましょう。
ソフトバンクでは、クラウド型のeラーニングシステムやオンライン研修にも使えるWeb会議ツールをはじめ、マネジメント層の教育や負担軽減、業務効率化に役立つ最新のデジタルソリューションを幅広く提供しています。自社に合うツール・サービスの種類やその活用方法に悩む場合は、一度ソフトバンクに相談してみるのも選択肢のひとつです。
関連セミナー・イベント
おすすめの記事
条件に該当するページがございません