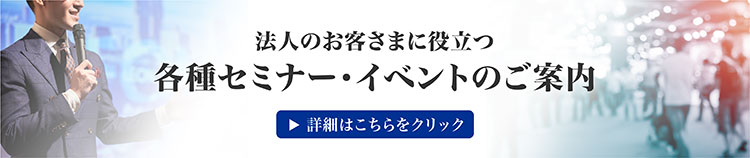フォーム読み込み中
労働時間は、労働基準法によって上限が設定されています。適正な賃金の支払い、長時間・過重労働の早期発見や防止など、企業はさまざまな観点で労働時間を適切に管理していくことが求められます。本稿では、労働時間に関する基礎知識や違反リスクなどについて辻・本郷 ITコンサルティング株式会社の菊池氏に解説いただきました。

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社
取締役
菊池 典明 氏
税理士。2012年辻・本郷 税理士法人大阪支部に入社。
株式会社のほか医療法人、社会福祉法人、公益法人等の税務・会計に関する業務を中心に、法人の事業承継や個人の相続コンサルティングも担当。
2015年より経営企画室に所属し、クライアントのクラウド会計の導入やDXの推進などに携わる。2021年よりDX事業推進室担当。
同年12月辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役就任。多くのセミナー講師も務める。
労働時間とは
労働時間とは、「労働者が雇用主の指揮命令下で働く時間」を指し、賃金計算の基準となります。就業規則や雇用契約書の記載にかかわらず、客観的に見て「雇用主の指揮命令下にある」と判断されれば労働時間とみなされ、企業には賃金の支払い義務が発生します。
この労働時間は、労働基準法で上限が設定されており、1日に8時間、週に40時間(10名未満の特例措置対象事業場の場合は週44時間)を超えてはならないと定められています。また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないとされています。例えば、9時から17時まで働き、その間の12時から13時まで休憩した場合、労働時間は7時間となります。
2019年の働き方改革関連法の施行以来、労働時間やこれに関連する論点への従業員の関心も非常に高くなっています。本稿で労働基準法における労働時間の定義や関連論点、違反した場合のリスクを確認しましょう。
労働基準法に違反した場合の罰則
労働基準法は労働条件の原則や最低基準を定めた基本的なルールであり、この法律を守ることは、企業の義務であり責任でもあります。また、労働基準法は強行法規であり、知らなかったでは済まされません。もし労働基準法に反するような行為があり、法律違反が認められた場合には労働基準監督署による是正指導を受けるばかりか、刑事責任を追及されたり、従業員から損害賠償を請求されたりすることもあるのです。
それでは、労働基準法に違反した場合、具体的にはどのような罰則があるのでしょうか。
先にも述べた通り、従業員に対して、原則1日に8時間、週に40時間を超える労働をさせることはできません。法定労働時間を超えて労働させた場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、従業員に休憩をとらせない場合も、労働基準法違反とみなされることがあります。休憩時間中に社内に待機させて電話をとらせたり、届いた荷物を受け取らせたりすることは実態として労働時間として取り扱われ、休憩が取得されていないとして違法となる可能性があります。従業員に休憩をとらせなかった場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
この他、従業員に休日をとらせなかった場合や残業代を支払わなかった場合にも、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるので注意しましょう。
労働基準法違反があれば、従業員の信頼を損なうばかりか、対外的な信用を失い、企業経営に支障をきたすこともあります。経営者や人事労務担当者などの労務管理に責任のある方は、労働基準法をよく理解し、労働基準法違反のないよう適切な労務管理を行いましょう。
労働時間の考え方
適切な労務管理のためにも、「労働時間」にまつわる用語の定義や考え方を確認しましょう。
法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法第32条に定められた「1日8時間・週40時間」を原則とする労働時間の上限を指します。過剰な労働を強いられることにより、労働者の健康が害されることを予防するため、法定労働時間が設けられています。
所定労働時間
労働基準法上の「法定労働時間」とは別に、労働時間の上限を定める概念として「所定労働時間」があります。
所定労働時間は、会社が独自に定める勤務時間のことです。主に、就業規則や雇用契約書などに記載された、休憩時間を除く始業から終業までの時間を意味します。なお、所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定めなければなりません。
実労働時間
実労働時間とは、労働者が労働義務から完全に開放されている休憩時間を除外した、労働者が実際に労働した時間のことを言います。一般的に、実労働時間は労働者が使用者の指揮命令の下に業務を行っている時間を指します。そのため、労働者の行為が使用者の指揮命令下でなされたものかどうかを客観的に判定することで、実労働時間が決まることになります。
例えば、始業時刻前であっても、作業前の点検や朝礼が実質的に使用者から強制されている場合は、実労働時間となり得ます。また、制服や作業着への着替えについては、労働者の自由意志で行われる場合は実労働時間に含まれませんが、就業規則や社内規定などで義務付けている場合には実労働時間として取り扱われることになります。
拘束時間
拘束時間とは、企業の拘束下にあるという意味で、実労働時間と休憩時間を合わせた時間を意味します。なお、「就業規則などで定められた始業時間から就業時間までの時間」に限定されるものでなく、時間外労働(残業時間)も含まれます。
休憩時間
休憩時間は、労働基準法第34条において、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定しています。
休憩時間は、従業員の肉体的・精神的な疲れを癒すために必要な時間です。そのため、このように労働時間に応じて適切な休憩を与えることが、義務付けられているのです。休憩時間は、文字通り従業員が休憩するための時間であるため、休憩時間中は仕事を課してはなりません。なお、この休憩時間はあくまで最低ラインです。したがって、例えば「7時間の労働で1時間の休憩を与える」「6時間以内の労働でも45分の休憩を与える」など基準を上回る長さの休憩時間を与えることは、従業員の心身に有利となるため全く問題ありません。
物流業界の労働力が不足している一方、宅配便の取扱個数は年々増加しています。2021年までの5年間で23.1%増、数にして約10.8億個増加したとされています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛要請などからECサイトを利用した宅配便が増加したためです。旅行やチケット販売等サービス分野、食品や生活家電、PC周辺機器など物販系分野のいずれも増加傾向にあり、EC市場のさらなる拡大が見込まれています。今後も宅配需要が高まる中で、トラックドライバーの確保や再配達を削減するなどの業務効率化が喫緊の課題と言えるでしょう。
それでは、あらためて働き方改革関連法の改正で変わることを確認していきましょう。
残業(時間外労働)と36協定による上限
ここまで見てきた通り、原則として、会社側は法定労働時間「1日8時間、週40時間」を超えて労働者を働かせる(=残業させる)ことはできません。しかし、労働者との間に「36(サブロク)協定」を結んでいる場合は、法定労働時間を超えた残業が認められています。
36協定とは、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を労働者にさせる場合に、労使間で結ぶ協定のことを言います。36協定の正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」であり、36協定という呼び名は、労働基準法第36条で規定されていることに由来します。36協定の届け出が必要となるのは、労働者が時間外労働を行う場合と、休日労働を行う場合です。
時間外労働について、36協定では、1日の労働時間が8時間を超える場合、もしくは週の労働時間が40時間を超える際に、会社は届出をおこなわなければならないとしています。ここで注意すべきポイントは、前項で取り上げた「所定労働時間」と「法定労働時間」の違いです。
例えば、9時出社で1時間の休憩をはさんで17時に退勤する場合、所定労働時間は7時間です。この際、18時間まで残業をして帰宅すると、1時間残業をしたということになります。残業を課す場合は36協定を結ぶのが原則ですが、このケースでは必要ありません。なぜなら、36協定が必要となるのは「法定労働時間」を超えて残業を行う場合であるからです。実働7時間に残業1時間をプラスしても労働時間は8時間になるため、法定労働時間は超えません。よって、36協定を結ぶ必要はないのです。

また、労働基準法では、1週間に最低でも1回、もしくは4週間を通して4回以上の休日を設ける必要があると規定しています。法定休日に労働を課す場合も36協定の締結が必要です。
例えば、週休2日制で1日の労働時間が5時間である会社の場合を考えてみましょう。この場合、2日ある休みのうち1日を休日出勤した場合、週の労働時間は30時間となるので、週の法定労働時間は超えません。また、週に1日の休日があるので、36協定を結ぶ必要はありません。一方、1ヵ月の休日を全て休日出勤した場合は、週の労働時間が35時間で法定労働時間は超えませんが、法定休日の要件を満たしません。そのため、36協定を結ぶ必要があります。
ところで、この36協定の適用対象外となる労働者や職種もあります。36協定は基本的に全労働者が対象となりますが、労務管理において経営者と一体的な立場にある管理監督者、派遣社員や業務委託者など直接雇用関係にない者に関しては36協定による時間外労働や休日の制限を受けません。なお、派遣社員については、直接雇用関係を結んでいる派遣元の36協定が適用されます。
また、後述する36協定の残業時間の上限規制が適用されない職種も存在します。具体的には、以下の職種が当てはまります。
- 建設業
- タクシーやバスなど自動車運転の業務
- 医師
- 研究開発業務
これらの職種は業務の進捗状況や季節によって労働時間が大きく異なったり、より柔軟な働き方が求められたりする職種であるため、36協定の適用除外とされてきました。ところが、研究開発の職種を除いて、2024年の4月から一部労働時間の上限規制が設けられるため、これらの職種に関連する企業は急ぎ対応が求められているのです。
▶関連記事:2024年問題とは?物流・運送業界が直面する課題とその解決策を分かりやすく解説
従来の労働基準法では、36協定を締結している場合であっても、残業時間の上限は設けられておらず、その結果、長時間労働が慢性化している企業が多く、社会問題となっていました。
これらの問題を是正するために、2019年4月に働き方改革関連法が施行され、その一環として時間外労働に上限が設定されたのです。具体的には、36協定を結んで労働者に残業を課す場合でも、原則月45時間、年360時間が上限となり、これを超えるような残業は違法となります。また、対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制を導入している場合、残業時間の上限は月42時間、年320時間となります。
上限を超えた残業を行う場合には、「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。特別条項付き36協定とは、繁忙期や突発的に発生した業務対応など特別の理由がある場合に月45時間、年360時間の上限を超えて労働者を働かせることができる協定です。2019年の法改正以前はこの特別条項に残業時間の上限規制がなかったため、実質は何時間でも働かせることができるという法の抜け道になっていました。これが長時間労働の温床となっていたため、2019年の法改正では特別条項にも残業時間に上限が設けられました。
特別条項付き36協定を締結した場合は月100時間未満(休日労働含む)、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させることができるのは1年につき6ヵ月までとされています。また、2~6ヵ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内(休日労働含む)におさまるようにしなければなりません。

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」をもとに作成
なお、36協定を締結せずに労働者へ時間外労働と休日労働を課した場合、使用者に6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があることは先に述べた通りです。36協定を締結しているにも関わらず、届け出をしていなかった場合も同様です。さらに、2019年の働き方改革関連法施行により、36協定で制限されている残業の上限時間を超過した場合も罰則が設けられました。特別条項で定められている規定に違反すると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。このように法律によって条件が明記されたため、これまで以上に正確な労務管理が必要になります。
労働基準法における休日の取り扱い
労働基準法に定められた休日を法定休日といい、会社で定めている所定休日と区別しています。法定休日は「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」と定められており、法定休日の労働には36協定だけでなく、割増賃金の支払いも必要です。
「毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日」については、回数の条件を満たしていれば、特定の曜日に休日を設定する必要はないため、土・日・祝日以外を休日としても法律上は問題ありません。また、労働基準法では、特に年間休日数を定めているわけではありません。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律ですから、週休制の原則を守っていれば、企業が独自に就業規則などで休日を増やしてもよいことになります。
一方で、労働基準法では労働時間を「1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならない」と定めています。そのため、1日8時間労働の会社では、週の休日を2日(法定休日と所定休日)設定し調整しているケースが多くあります。これらを前提として、年間365日(52.14週)を考慮すれば、年間で105日が公休を含めた年間休日の最低ラインとなります。
パート・アルバイト・派遣社員の場合も規則に違いはない
労働基準法では職業の種類に関係なく事業に使用される者で、賃金を支払われる者は全て労働者に該当し、労働基準法が適用されます。それは正社員・契約社員・嘱託などさまざまな雇用形態であっても同じです。したがって、時間給で雇用し、週の勤務時間がまちまちのパートやアルバイトにも労働基準法が適用されます。
なお、派遣社員についても注意が必要です。業務に関する指揮命令権に関しては、派遣先会社が持つことになりますので、派遣社員の労働時間、休憩・休日などの管理は、派遣先会社が行うことになります。そのため、派遣先会社の就業規則を派遣社員に及ぼした方が合理的であることから、派遣元会社の就業規則で、「派遣先の就業規則に準じる」と定められていたり、別途、就業条件明示書、労働条件通知書などで派遣先の就業規則に則った内容を定めたりするケースが多くあります。
労働時間として認められる/認められない時間を整理
ここでは労働時間として認められる時間/認められない時間を整理してみましょう。
労働時間とは、これまで見てきた通り、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。言うまでもなく、ここでのポイントは「使用者の指揮命令下に置かれているか否か」です。労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決められるものではなく、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけられたものといえるか否かなどによって判断されるのです。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、以下の時間は労働時間に含まれるとされています。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
これらを踏まえて労働時間として認められる/認められない時間を整理すると以下のようになります。ただし、あくまでも労働時間に含まれるか否かは、客観的事実によって判断が異なりますので、ご注意ください。特に昨今はリモートワークの普及などにより、休日のメールや電話対応、持ち帰りの仕事も容易になったため、労働時間の判断がより困難になっていますので注意が必要です。
| 労働時間として認められる | 労働時間として認められない |
|---|---|
|
|
労働時間にまつわる課題
ここまで労働時間の定義や対象となる範囲を整理してきましたが、労働時間にまつわる課題は山積しています。特に、働き方改革による「長時間労働の是正」への対策が急務となっています。
働き方改革関連法における労働時間に関する制度の見直しについては、労働者の長時間労働を防止するために、今まで上限のなかった36協定に時間外労働の上限規制が導入されます。原則として時間外労働の上限が月45時間・年360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間・年320時間)となります。繁忙期など事情がある場合に認められる特別条項でも時間外労働は年720時間(複数月平均80時間)を上限としています。また、特別条項ではさらに月45時間を上回る回数は年6回まで、1ヵ月100時間未満などと規定しています。違反した企業、雇用主には6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。長時間労働に頼ってきた業種・業態も少なくないと思われますが、このようなケースにおいては経営の在り方を根本から見直す必要があるでしょう。
また、残業代の未払いをはじめとした労使トラブルも大きな課題です。働き方改革もあり、労働者の権利意識の向上から、働いた分の残業代を正当に請求する風潮が高まっています。このため、突然従業員から残業代を請求されるケースも少なくありません。未払い残業代がある場合、従業員が労働基準監督署に申告する可能性があります。従業員の申告によって立ち入り検査が行われると、法令違反があるときは是正勧告がされ、法令違反はないものの改善が望ましいときは指導票の交付がなされます。是正勧告に強制力はありませんが、指摘事項を改善しない場合や悪質と判断された場合には、懲役や罰金が科される可能性があることは先に述べた通りです。それだけでなく、残業代が正当に支払われないと、従業員のモチベーションが低下し、仕事の質が悪化することが懸念されます。さらに、労働基準局から是正勧告を受けたり、従業員からの残業代の未払い訴訟が起こったりすると、企業イメージの低下につながる恐れがあります。
労働時間の正確な管理にはデジタル化が不可欠
ここまで見てきた通り、労働時間の正確な管理がこれまで以上に求められますが、働き方改革への対応が求められることに加え、リモートワークの普及、フレックスタイム制や直行直帰などにより働き方は多様化しており、労働時間をアナログに管理するには限界があります。例えば、タイムカードによる労働時間の管理は、月末の集計が前提となっており、残業時間の管理がしづらく、月末になってはじめて残業時間の上限オーバーが発覚するという事態にもなりかねません。
法令を遵守し、かつ、多様な働き方にも対応するためにも、労働時間をデジタルに管理することが必要と言えるでしょう。
条件に該当するページがございません
関連セミナー・イベント
おすすめの記事
条件に該当するページがございません