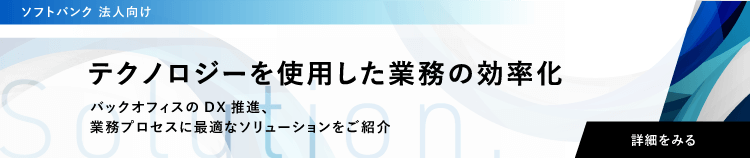フォーム読み込み中
近い将来、日本の多くの企業では、既存のITシステムが老朽化することで、事業のさらなる拡大、企業の成長が妨げられる「2025年の崖」と呼ばれる問題が生じると警告されています。これを回避するため、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)への取り組みを始めています。
経済産業省も2018年に、日本企業がDXを進める動きを加速すべく、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」を発表しました。しかし現状では、DXに取り組み始めたものの成果が感じられないという企業が多いようです。
まずは、DXの定義をあらためて確認し、なぜDXへの取り組みが必要と言われているのか理解しましょう。その上で、成果を出している企業の事例も参考にしながら、自社に最適な方法を選んで取り組むことが大切です。今回は、DXとは何かを見直すとともに、DXを進めるうえでの課題や、導入成功に必要な要素について紹介します。
DXの定義とは
DXが最初に提唱されたのは2004年のこと。もともとDXとは、スウェーデンのウメオ大学教授、エリック・ストルターマン氏が主張した「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念のことを指します。
近年では、一般的に「最新のデジタル技術を駆使した、デジタル化時代に対応するための企業の変革」という意味合いのビジネス用語として使われています。
なお、先述の「DX推進ガイドライン」では、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と、より詳細に定義しています。
企業がDXに取り組むべき理由

なぜいま、日本の企業には、DXの推進が求められているのでしょうか。企業がDXに取り組むべき理由は、主に次の3つです。
1. 既存システムの老朽化・ブラックボックス化
1つ目の理由は、「2025年の崖」と呼ばれる現象と関係しています。DX推進ガイドライン策定に先がけて、経済産業省が2018年にまとめた報告書「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」(以下、DXレポート)によると、多くの企業において、既存のITシステムの老朽化、ブラックボックス化が起きているといいます。
ブラックボックス化とは、カスタマイズを繰り返したためにプログラムが複雑化した状態、システムを構築した担当者が退職したなどにより、システムの全貌が解明できなくなった状態のことです。DXレポートでは、このように老朽化、ブラックボックス化した既存システムが、新しい事業展開に対応できない、保守・運用のためのコストがかさむといった問題を生み、DXの推進を阻んでいると指摘しています。
同レポートには、さらに、企業がこうした既存システムの問題を解消できない場合には、2025年以降、日本経済に年間で最大12兆円(現在の約3倍)の損失が生じる可能性があるという衝撃的な内容も記されました。これがいわゆる「2025年の崖」です。
成長を追い求めることは企業の経営者にとって優先事項の一つですが、既存システムを使い続けている限り、これ以上の成長を見込むことは難しいでしょう。「2025年の崖」を目前に控えたいま、システムの刷新を含むDXは、ほとんどの日本企業において無視できない重要な課題です。
2. 消費行動の変化
2つ目の理由は、消費者のマインドや行動の変化です。近年、消費者の多くが、商品そのものを買うことよりも、商品やサービスを購入することで得られる体験の質を重視するようになってきました。いわゆる「モノ消費」から「コト消費」への移行が進んでいるのです。
また、近年では、余っているものや場所を無駄にせず、みんなで共有して使うという新しい価値観と消費の形が生まれました。カーシェアリングやシェアサイクルといったシェアリングエコノミー型のサービスが人気を集めています。
今後は企業もこの流れに対応して、消費者に価値あるコトや魅力的で特別な体験を与えられるような、新たなビジネスモデルを模索しなければなりません。そのためには、システムはもちろん、業務や組織全体をも変革する必要があるのです。
3. デジタル化によるビジネス環境の激変
3つ目の理由は、DX推進ガイドラインにおけるDXの定義でもふれられている「ビジネス環境の激しい変化」です。
あらゆる分野で、デジタル技術を駆使した革新的なビジネスモデルを展開する新規参入者が登場し、既存の産業を揺るがす「デジタルディスラプション」と呼ばれる現象が起こっています。たとえばamazon.com(アマゾンドットコム)は、巨大なプラットフォームを構築して本や音楽CDをオンラインで買うという新たな買い物スタイルを生み出し、それまで店舗での販売を中心に展開していた書店やCDショップに打撃を与えました。
アメリカのUber(ウーバー)やAirbnb(エアービーアンドビー)も、デジタルディスラプションを起こした企業として知られています。ウーバーは、スマートフォンアプリやWebサイトを使って、一般の登録ドライバーと、車で目的地まで移動したいユーザとをつなぐ配車サービスです。エアービーアンドビーは、ウーバーの不動産バージョンともいうべきもので、アプリやWebサイトを通して、空き部屋を貸したいホストと部屋を借りて宿泊したい旅行者とをつなぐサービスです。
いずれも先述のシェアリングエコノミーの代表例ですが、自社では車や建物を所有せず、すでに誰かが所有しているのに使われていない車の座席や部屋を活用した点が画期的でした。ウーバーはタクシー代わりに、エアービーアンドビーはホテル代わりに使われるケースが多く、タクシー業界やホテル業界をおびやかす存在になっています。
このように、人々の価値観を覆し、新たな生活スタイルをもたらすような製品やサービスが次々と生まれ、ビジネス環境が大きく変わりつつあります。そのなかで既存の企業が生き残るためには、DXの推進が不可欠だと考えられているのです。自社が身をおく業界でデジタルディスラプションが起こってからでは、もう手遅れかもしれません。どの業界・企業においても、変革は急務といえるでしょう。
成功者から分析した6つの成功要因

DXがなかなか進まない企業も多い中、すでにDXの取り組みを始め、成果を出している企業も存在します。富士通は、2019年に欧米各国や中国、日本など世界9ヵ国のビジネスリーダー900人を対象とした調査を行い、DXへの取り組み状況やDXの成功要因などを「グローバル・デジタルトランスフォーメーション調査レポート2019」にまとめました。
同レポートによると、回答者の87%がDXへの取り組みを検討、試行、実践したと回答。DXへの取り組みがかなり広がっていることがうかがえます。一方、実践して成果を挙げたと回答した企業の割合は、全業種で36%。業種別では、金融業で47%、運輸業で45%が成果を挙げたと答えており、特にこの2業種でDXが進んでいることが分かります。
なお、同レポートでは、調査結果を分析したところ、DXで成果を出した企業は、以下の6つの要素において高い能力を持つことが確認できたといいます。
リーダーシップ:CEOの優先課題としてDXに取り組む
エコシステム:パートナーとともに、トラステッドな(信頼性のある)エコシステムを構築
人材のエンパワーメント:必要なスキルを持つ人材を育成し、成長の機会を与える
アジャイルな文化:イノベーションに挑戦し、変化に対応する文化を醸成
データからの価値創出:セキュリティを確保し、信頼性のあるデータからビジネス成果を生み出す
ビジネスとの融合:デジタル技術をビジネスプロセスに組み込み駆動する
出典:「グローバル・デジタルトランスフォーメーション調査レポート2019」(富士通)
このうち特に注目したいのは、「リーダーシップ」「エコシステム」「人材のエンパワーメント」の3つです。DXの推進において、経営トップが強いリーダーシップを持って取り組むことが重要なのは言うまでもありません。富士通の調査では、リーダーが従業員に向けて積極的に会社の経営状況などを発信し、情熱を持って自らの考えを伝える「共感型リーダーシップ」を発揮している企業のほうが、そうでない企業よりDXで成果を挙げていることが明らかになっています。
また、エコシステムを活用している企業のほうが、活用していない企業よりもDXで成果を挙げていることも分かっています。エコシステムとは、もともとは「生態系」を意味する言葉ですが、ビジネスにおけるエコシステムとは、ひとつの大企業が単独で事業を展開するのではなく、ある業界内で多数の企業が連携と分業によって収益を高めていく仕組みを指します。同調査では、多くのビジネスリーダーが、エコシステムが有効に機能するためには、情報共有や役割の明確化、パートナー企業を平等に扱うことが重要だと答えています。
さらに同調査では、リーダーがワークライフバランスやダイバーシティ(多様な人材の活用)、インクルージョン(多様な人材の個性を尊重し、それぞれが最大限に能力を発揮できるようにすること)を重視し、従業員に自発的な行動をうながしている企業のほうが、そうでない企業よりもDXで成果を生み出す傾向があるとされています。DXには、デジタル技術に関する知識やスキル、新しい事業を生み出す創造性を持った人材が不可欠です。DXを成功に導くには、リーダーが責任を持ってそのような人材をエンパワーする(育成し、能力を発揮させる)ことが重要だというのです。
まだDXに取り組めていない企業や、取り組んではいても成果を実感できていない企業にとっては、これらの要素を意識し、体制づくりの参考にすることが前進のカギとなりそうです。
DX実現に必要なテクノロジー

DXには、最先端のデジタル技術の力が不可欠だといわれています。では、どのような技術がDX推進を支えてくれるのでしょうか。代表的なものを紹介しましょう。
クラウド
メールソフトなどのソフトウェア、サーバ、ストレージなどのインフラを自社内に持っていなくても、インターネットを通じてそれらの機能を利用できる仕組みのこと。近年は、多種多様なクラウドサービスが提供されています。
各事業や業務に適したクラウドサービスを選ぶことで、AIなど最先端のデジタル技術が活用しやすくなり、ビジネスがスピードアップするというメリットがあります。また、自社で所有し管理するオンプレミス型のシステムからクラウドに移行することで、システムの維持費の削減につながる場合もあります。
AI
学習や言語の理解、予測、問題解決など、人間にしかできないと考えられていた知的な行動の一部を、コンピュータで再現する技術のことです。ビジネスでのAI利用は急速に普及しつつあります。AIによる顔認識や音声認識機能を使って新商品を開発する、膨大な顧客データをAIで分析して新サービスに生かす、問い合わせ対応にAIを導入するなど、さまざまな用途で使われています。
IoT(Internet of Things)
車や家電など、これまでインターネットに接続されていなかった「モノ」をインターネットにつないでモノの状態や人間の行動などの情報を収集・分析し、得られたデータを活用することで、新たなサービスを生み出す技術です。
ある大手農機メーカでは、農業機器にセンサを取り付け、機器から発信される稼働情報をもとに、農作業の効率化を支援するIoTのサービスを提供しています。また、最寄りの無人駐車場で気軽に車を借りて返却できるカーシェアリングが人気ですが、このサービスにも、車の位置情報や利用時間などを把握するためにIoTの技術が使われています。
5G
「5th Generation」の略で「第5世代移動通信システム」のことです。現在使われている4Gから5Gになることで、通信速度が約20倍(4Gとの比較においての想定倍率)になり、10倍の端末への同時接続が可能になると言われています。端末の同時多接続ができるようになれば、IoT化が加速する可能性があります。
そうなると、大容量の高精細なデータを送受信できるようになるため、遠隔地にいてもオンラインで医師の診療を受けられたり、離れた場所にいる人と一緒に楽器演奏の練習をできるようになるとも言われているのです。
モバイル
移動先や外出先で通信できる技術のこと。一般的には「モバイル」というと、スマートフォンや携帯電話、タブレット型PCといったモバイル端末を指す場合が多いかもしれませんがDXにおいてはそれらモバイル端末を活用してビジネス活動を行うことを指します。具体的には、社外での商談中に社内のシステムにアクセスする、在宅勤務中に社内会議に参加するといった、時間や場所にしばられない働き方を可能にする通信技術です。使い方次第で、業務の効率化や社内コミュニケーションの活性化にもつながります。
DX実現のための理想的な支援

先述したように、DXを進めていくにはテクノロジーの存在が欠かせません。企業に通信インフラを提供してきた通信事業者の必要性は、これからますます高まると考えられます。
最先端のデジタル技術をソリューションとして提供するとともに、その運用をサポートしてきたソフトバンクは、多くの企業から信頼を寄せられています。ソフトバンクを相談役としてDXの取り組みを始めるのも、最適解のひとつといえるでしょう。その中でもエンジニアをはじめ幅広い職種のスペシャリストを備えたソフトバンクのDX本部では、医療や物流などさまざまな分野で企業のDXを支援するとともに、パートナー企業との新規事業の共創を進めています。
DXを実現させるためには、テクノロジーだけでなく、データを最適な形で活用する必要があります。しかし、日本企業の多くは、データを活用したDXに行き詰まっているのが現状です。そこで、2019年、ソフトバンクと広告会社の博報堂、テクノロジー企業のArmは、デジタルマーケティングの分野でデータを活用して変革に取り組む企業を支援しようと、インキュデータ株式会社を設立しました。
連携する3社のうちArmは、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)と呼ばれる、顧客一人一人の属性・行動データを統合して管理するデータプラットフォームを開発してきた企業です。インキュデータでは、Treasure DataのCDPである「Treasure Data CDP」に蓄積されるクライアント企業の顧客データをベースに、通信事業者であるソフトバンクが集めてきた独自の情報を匿名化したデータ、博報堂グループが保有する生活者データベースを組み合わせて、より高度なデータ分析を行っていくといいます。
ソフトバンク、博報堂、Armという3社が持つデータ分析技術とデータ活用ノウハウを合わせることで、より効果的なマーケティング施策の立案、実施のほか、データを活用した新規事業を支援することもできるようになると期待されています。
ホワイトペーパー無料公開中『DXが次世代企業戦略の中枢になる理由』
DXを推進する上での課題

ここまで、DXを推進すべき理由や成功要因、推進に必要なテクノロジーなどを確認してきました。一方で、必要性は感じていてもまだ実施に至っていない企業や、実施しても成果を出せない企業が多いという現状があります。
これらの企業では、何がDXの推進を阻んでいるのでしょうか。DXを進める上で課題となりうる要素を確認しておきましょう。
既存システム
多くの企業において、すでに既存システムは老朽化し、技術面でも機能面でも限界を迎えつつあります。先述の通り、ブラックボックス化しているケースも少なくありません。このような既存システムの状態が、DXを進める上で足かせとなっています。
また、事業部門ごとにそれぞれが最適と判断した異なるシステムを使ってきたために、企業全体でのデータ管理や連携ができず、DXが思うように進められないというケースもあります。また、特定のベンダ(メーカ)の独自の技術に依存したシステムを導入した結果、後から他ベンダのサービス、システムに乗り換えにくくなってしまう「ベンダーロックイン」という現象も問題になっているのです。
資金不足
「DXレポート」によると、日本企業のIT関連予算の8割は、現行ビジネスの維持・運営に充てられています。つまり多くの企業では現状維持が精一杯で、システムの刷新や新たなIT戦略に資金を充てることができていないのです。
企業によっては、老朽化、ブラックボックス化した既存システムの維持費が大きな負担となっているケースも少なくないようです。
人材不足
DX推進には、AIやIoTといった最新のデジタル技術に詳しい人材や、デジタル技術を生かした新たな事業・サービスを企画できる人材が必要です。しかし多くの企業では、自社での人材育成が遅れている上に、社外から確保することも困難という厳しい状況です。
DXの事例

では、実際にDXを推進し、成果を出している企業は、どんな取り組みを行っているのでしょうか。具体的な事例をいくつか紹介しましょう。
イオン九州のラストワンマイル配送
福岡市に本社を置き、九州エリアでスーパーやホームセンターなどの小売店舗を展開するイオン九州株式会社(以後、イオン九州)。同社は2019年に、イオン九州店舗からの商品配送をICT(情報通信技術)によって効率化するため、物流分野においてソフトバンクとの協業を始めました。
近年、共働き世帯の増加や高齢化によりネットスーパーの需要が高まっています。特に九州では高齢化の影響が大きく、店舗まで商品を購入しに行くことに不便を感じる人が増えており、ネットスーパーが問題の解決策になると考えられています。
しかしネットスーパーの配送業務では、日によって顧客宅への荷物の量が異なるにも関わらず、常に配送車両のトラックを一定数確保しなければなりません。そのため余分なコストがかかる、もしくはトラックを確保できず、急な需要の変化や即日配送、夜間配送にまでは対応できないといった課題があります。配送の時間帯が限られていると、生鮮食品のような、顧客がすぐに入手したいと望む品については、なかなか利用が広がりません。
そこでイオン九州は、ソフトバンクの力を借りながら、デジタル技術を活用して需要に応じた配送車両の手配やコストの削減を実現し、顧客宅への夜間配送(ラストワンマイル配送)という新しい取り組みを進めることにしたのです。
両社はまず2019年6月より、イオンショッパーズ福岡店のネットスーパーの注文品を、夜間22~23時を含む時間帯に顧客宅へ配送する実証実験を実施し、夜間配送の需要について調査しました。
さらに両社は、ネットスーパーの注文品を顧客宅まで配送する業務を、地域の配送ドライバーとマッチングするシステムの実証実験にも取り組んでいます。ソフトバンクの協業パートナーであるCBcloud株式会社の配送マッチングサービス「PickGo」を活用し、必要なときに地域の登録ドライバーとつなぐことで、荷物の量に応じた車両数だけを無駄なく手配し、配送を行います。
両社は実証実験の結果を踏まえ、さらなる配送時間の拡大、顧客の利便性の向上を目指すと発表しています。より顧客のニーズに合ったサービスの実現を目指すDXの一例として、注目したい取り組みです。
梓設計の革新的なワークプレイス実現に向けた取り組み
大手組織建築設計事務所である株式会社梓設計(以下、梓設計)は、ソフトバンク、IoTサービス事業のウフルと連携。2019年9月30日から2020年7月末まで、東京都大田区にある同社の本社にて、革新的なワークプレイスの実現に向け、実証実験を行っています。
働く人のパフォーマンスを最大化させる環境の条件や指標を調査するため、社内に、温湿度や照度、騒音、におい、気圧などの環境データを取得できるセンサや、会議室の利用状況を確認できる人感センサを設置。
会議室内にはカメラやマイクを設置して映像および音声データを収集するほか、一部の社員がメガネや腕時計型のウェアラブル機器を身に着けて、感情や心拍数に関するデータを収集し、環境センサから収集したデータとの相関性を分析するといいます。
将来的には、今回の実験結果と、建物の立体モデルを構築するプロセスである「BIM(Building Information Modeling)」を連携させて、より高度な分析を行い、働く人のパフォーマンスを最大化させるワークプレイスの実現に役立てるとしています。
この革新的なワークプレイス実現のための実証実験は、最先端のIoT技術を駆使したDXの取り組み例であり、専門のノウハウを持つ複数の企業が連携することにより、成果に結びついた一例といえるでしょう。
まとめ:資金や人材をそろえ、DXを推進できる体制づくりを
デジタル技術やデータの活用によって、これから先、ビジネスをめぐる環境は激変していくと予想されます。現状で事業が安定していたとしても、将来的に同じ状況が維持できるかどうかは分かりません。既存のシステムはいずれ老朽化し、そのシステムを維持するためのコストや人材が負担となって企業にのしかかるでしょう。「2025年の崖」に直面してから新規事業や変革を始めようとしても、身動きがとれなくなっている可能性もあります。
この問題を回避するためには、迅速にDXへの取り組みを推進し、成果を出せる体制をつくり上げる必要があります。まずは自社の現状を客観的に分析し、既存のシステムが老朽化や複雑化、ブラックボックス化しているのであれば、具体的な対処法を検討しましょう。
DXを成功させるには、まずは経営トップがデジタル技術の重要性やDXの意義を理解し、経営戦略を明確にする必要があります。方向性を定めないまま、自社流のやり方でDXに取り組みはじめると、後に技術面で壁にぶつかり、混乱の修復に時間がかかる場合もあります。
今回紹介した事例からも分かるように、DXの推進やデジタル化時代の事業展開には、多様な外部企業の力が欠かせません。DXにおいて豊富な実績を持つソフトバンクには、新たな体制を支援する技術がそろっています。デジタル技術やデジタルビジネスに精通した専門企業に早い段階で相談し、支援を受けることも、成功への近道ではないでしょうか。
関連セミナー・イベント
おすすめの記事
条件に該当するページがございません