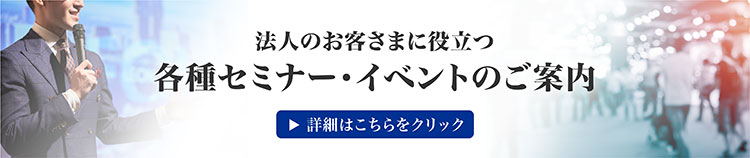フォーム読み込み中
2023年以降も怒涛の法改正が控えており、大きなところでは、「インボイス制度」も2023年10月から開始されました。本記事では「電子化編」「インフラ編」「働き方編」の3つのカテゴリに分け、中小企業への影響度が大きい2023年以降の法改正情報をピックアップしています。対策への道のりは考慮すべきことが多いですが、正しく情報をキャッチし、早めに具体的な対策を進めていきましょう。
【誤った情報の提供についてのお詫び】
記事中の記載につきまして一部誤りがあることが判明いたしました。該当部分を修正するとともにお詫びいたします。
また、今後はこのような事態が起こらぬよう、より一層の注意を払って情報収集・確認を行い、正確な情報をご提供できるように努めてまいります。読者の皆さまにはご迷惑をお掛けしてしまったことを心よりお詫び申し上げます。
<喫緊の対応が求められる6つの法改正>

【電子化編】
インボイス制度のスタート・・・消費税法
◆施行日:2023年10月
◆対象:全ての事業者
消費税法の改正により、いわゆる「インボイス制度」が導入されました。
売手が買手に対して、正確な税率(8%か10%)や消費税額など法令で定められた内容が記載された適格請求書(インボイス)を交付する制度です。
買手からすると、売手が発行したインボイスがないと仕入税額の控除※ができず「納税負担が増えて」しまいます。受け取ったインボイスに必要事項が記載されているかチェックが必要です。
売手は買手がインボイスの発行を求めてくるため応じなければなりません。発行できないことを理由に仕入税額控除分を考慮した調整が入ったり、取引を躊躇される可能性もあります。
※仕入税額控除(納付税額を計算する際に、課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くこと)
制度開始にあたり、売手・買手に求められている実務上のポイントは以下の通りです。
≪売手≫
・適格請求書発行事業者の登録(2023年9月30日まで)
・必要事項が記載されたインボイスの発行
・インボイスの写しを保管(7年間)
≪買手≫
・売手が適格請求書発行事業者か確認
・必要事項が記載されたインボイスかどうか確認
・交付されたインボイスを保管(7年間)
→電子データで受け取ったインボイスの場合は電子帳簿保存法に則って保存が必要(詳細は電子帳簿保存法の章で紹介)
2023年10月に制度がスタートし、自社の請求書管理などで作業工程が煩雑にはなっていないでしょうか。取引先を巻き込む重要な法改正になりますので、着実に対応を進めていきましょう。
◆関連セミナー:(木曜日定期開催!)インボイスの「制度」と「具体策」の両方がわかるおススメの勉強会
※freee株式会社のWebサイトに遷移します
電子取引は電子保存必須!・・・電子帳簿保存法
◆施行日:2022年1月施行済み(2023年12月31日で宥恕期間終了)
◆対象:事業者規模を問わず、税務申告を行う全ての法人・個人事業主
電子帳簿保存法は、国税関係帳簿や国税関係書類について一定の要件を満たせば電子データで保存できると定めた法律です。1998年から施行され、徐々にIT技術の取り入れや業務実態に沿った形にルールが緩和されています。
電子データとして保存する方法は以下の3つに区分されます。
≪3つの保存区分≫
・電子帳簿等保存:自己で一貫してPC等で作成した帳簿・書類をそのまま電子保存
・スキャナ保存:自己で紙で発行、または相手から紙で受領した書類をスキャンして画像データとして保存する
・電子取引の電子保存:メール・EDIなどで交付・受領した書類をそのまま電子保存する(※電子データで受け取ったインボイスも電子取引の要件で保存が必要)
≪帳簿・書類ってどんなもの?≫
帳簿:総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳など
書類:決算書類(賃借対照表・損益計算書など)、取引関係書類(見積書・発注書・納品書・領収書など)
上記のうち「電子取引」は、これまでは受領した取引情報が電子データでも、紙に印刷し保存することができました。しかし、2022年1月の改正でそのルールは廃止され、「電子データは電子データのままで保存(紙への出力保存はNG)」※することが義務付けられました。違反した場合、重加算税の10%加重や青色申告の取り消しなどが科される可能性があります。
※ 2023年度の税制改正大綱により、2024年以降も一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能
この「電子取引」に関する要件は、移行準備が整わない事業者への配慮として、引き続き紙で保存できるよう経過措置がとられています。その経過措置も2023年12月31日で終了します。早めに電子データでの保存が可能なシステムや企業体制を整備していきましょう。
【インフラ編】
アルコールチェッカー使用の義務化・・・道路交通法
◆施行日:2022年4月施行済み(アルコールチェッカー使用義務化は2023年12月1日より開始)
◆対象:安全運転管理者を配置している企業(定員11人以上の車を1台以上または白ナンバー車を5台以上使う企業)
2022年4月から物流や運輸業だけでなく、自社の荷物や人を運ぶ「白ナンバー」車への点呼・アルコールチェックが義務化されました。2023年12月からはアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの義務化も開始されるため、多くの企業でアルコールチェッカーの配備とその管理体制の整備が進められています。
アルコールチェックを怠った場合、安全運転管理者の業務違反となり「安全運転管理者の解任命令」が出される可能性があります。実質的な業務停止に陥らないよう準備する必要があります。検知器の選定を行うとともに、すでに開始している点呼や記録の運用をする中で、非効率な部分があれば見直すなど対策をしていきましょう。
≪2023年12月より開始される道路交通法義務化規定≫
・アルコールチェッカー使用での酒気帯び確認:
呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器が必要
・アルコールチェッカーを常時有効に保持:
正常に作動し、故障がない状態でアルコールチェッカーを保持しておくことが求められる(メンテナンスが必要)
一部のアナログ簡易無線が使用不可に・・・電波法
◆施行日:2021年9月1日(一部のアナログ簡易無線機の使用期限を2024年11月30日と規定)
◆対象:アナログ簡易無線機を利用の企業
現場で働く従業員のコミュニケーション手段として、広く利用されている無線機のうち、一部のアナログ簡易無線機については2024年11月30日を期限として使用できなくなります。期限以降に対象の無線機を誤って使用した場合、「電波法違反」となり処罰の対象になります。
≪必要な対策≫
・使用期限の過ぎた周波数を使用できないようにする対策:
機器への停波措置を行なう
・無線機運用を継続する場合は代替手段の検討:
IP無線アプリやデジタル無線機への移行などの機器選定
全ての無線機やトランシーバーが廃止になるわけではありません。自社で利用している無線機が廃止となる周波数を使っているかどうかなど、取扱説明書やメーカへ問い合わせしましょう。
現場業務に欠かせない機器であるため、業務に影響が出ないよう移行のスケジュールは計画的に立てていきましょう。
▶関連記事:2024年12月から無線機やトランシーバーが使えなくなる?~電波法関連法令の規定による期限到来
【働き方編】
時間外労働の割増賃金率引き上げスタート・・・労働基準法(中小企業)
◆施行日:2023年4月1日
◆対象:中小企業(資本金額・従業員数などの詳細定義あり)
大企業で先行して改正されていた、時間外労働の割増賃金率引き上げが中小企業でも開始されました。長時間労働の抑制が目的で、時間外労働が月60時間を超える場合は、超えた時間に対して割増賃金率が50%以上に引き上げられます。(現行25%)
≪必要な対策≫
・日々の適正な労働時間の把握:
正しい時間外労働時間の管理と割増賃金率での給与計算が求められる
・代替休暇への振替:
割増賃金の代わりに有給の休暇付与ができるため、その計算・振替の対応
・超過しそうな従業員への残業抑制や業務調整:
超過した(しそうな)場合に従業員に対してアラートを出せる仕組みなどが必要
従業員一人一人の労働状況に応じた割増賃金率を適正に管理することが求められるため、制度への正しい理解が必要です。できる限り長時間労働が発生しないよう、業務プロセスや労働環境を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
◆関連リンク:厚生労働省リーフレット
労働時間上限規制適用が拡大・・・労働基準法(建設等特定4業種)
◆施行日:2024年4月1日
◆対象:建設・自動車運転業務・医師など
36協定※で定める時間外労働は最大でも月45時間/年360時間以内です。しかし、時間外労働の上限設定には例外措置がありました。臨時的に特別な事情で限度時間を超える労働が必要な場合は「特別条項付き36協定」を結ぶことで上限を超える労働をさせることができたため、事実上労働者を無制限に残業させることが可能でした。
そこで2019年4月からこれまで無制限だった時間外労働の上限規制が行われました(中小企業は2020年4月から)。建設業をはじめとする上記対象業種においては、5年間の猶予期間が設けられていましたが、その猶予も期限を迎えることになります。
※36協定(企業が法定労働時間である1日8時間/1週間40時間を超えて労働や残業を命じる場合に、労使間で取り交わされる協定のこと)
≪改正後の特別条項付き36協定における時間外労働の上限規制≫
①年720時間以内 ②月100時間未満 ③2~6ヵ月平均80時間以内 ④月45時間超は年6回が限度
(②,③は休日労働も含む)
≪必要な対策≫
・適正な労働時間の管理:
時間外労働の時間帯・時間数・休日かどうかなどを細かく把握が必要。それらを集計し保存することが義務付けられている
・労働基準監督署へ36協定の新様式による届け出:
2021年4月以降新様式となり、押印署名などが廃止。より便利な電子申請も可能
・業務調整や残業抑止:
超過した(しそうな)場合に従業員に対してアラートを出せる仕組みなどが必要
◆関連記事:建設業の2024年問題とは? 働き方改革に向けた課題と解決策
働き方編であげた2つの法改正では、アナログな管理方法を継続していると知らず知らずのうちに法令違反をしてしまう可能性が出てきます。時間外労働の把握は、よりリアルタイムな状況把握が求められています。管理者が手を動かさなくても、対象者へのケアをよりスピーディに行える環境を整えていきましょう。
勤怠管理の効率的な方法に関しては以下の記事を参考にしてみてください。
2023年以降も法改正が盛りだくさん
いかがでしたでしょうか?
正しい理解が求められ、より慎重に対応する必要がある法改正。
ソフトバンクは各法改正への対策を無理なく進めるために、2023年もデジタルを活用した支援策や役立つ情報を発信してまいります。
ぜひ皆さまの取り組みの参考にしてみてください。
関連セミナー・イベント
おすすめの記事
条件に該当するページがございません