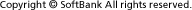東日本大震災の発生から10年目となる2020年。復興応援ソング『花は咲く』の作詞をはじめ、これまでさまざまな支援を続けてきた宮城県出身の映画監督・岩井俊二さんにインタビュー。いま改めて、震災当時のこと、震災後に生まれた視点や気づき、そしてより良い未来に向けて、私たちはどう向き合っていけばいいのかをお聞きしました。
プロフィール

岩井俊二
1963年、宮城県仙台市生まれ。1988年よりドラマやミュージックビデオをはじめ、多方面の映像世界で活動。1994年『undo』で映画監督としてのキャリアをスタート。1996年『スワロウテイル』、2001年『リリイ・シュシュのすべて』、2004年『花とアリス』など数々の作品を発表。2012年には岩井監督が様々な人々と東日本大震災後について語り合うドキュメンタリー作品『friends after 3.11【劇場版】』を発表。復興支援ソング『花は咲く』の作詞も手がけ、岩谷時子賞特別賞を受賞している。2020年1月17日に公開された映画最新作『ラストレター』は岩井監督の出身地・宮城県でロケが行われた。
目次
遠く離れた地から、家族や友人の無事を願った

2020年3月11日で東日本大震災から10年目を迎えます。当時の記憶をお聞かせください。
当時、僕はロサンゼルスに滞在していて東京にいるスタッフと電話でやり取りをしていました。スタッフがものすごく大きな地震が発生したと言うので、日本のニュースチャンネルをつけたところ、震源が郷里の宮城県沖。東京でそれほどまでに揺れているのなら、震源地の宮城県はどうなっているのだろう……と一気に不安が襲ってきました。テレビを眺めていると津波の映像も流れ始め、遠く離れて時差もあるアメリカにいながら、まるで日本にいるかのような感覚で過ごしていました。
家族に連絡がつかなくなり、消息がわかる2、3日後まではとにかく心配でした。宮城に親戚が多く、ある人はふと外に目をやると目線の高さまで浸水していて、あわてて逃げて何とか助かったという話も聞きました。塩竃(しおがま)に住む親戚はビルのずいぶん高いところに避難したそうです。ビルから下に見えるショッピングモールに津波が押し寄せる様子を撮影した動画を見せてもらったのですが、その動画を見て大きな衝撃を受けました。
自身の実体験から作品を発表

実際に被災地を訪れたそうですが、その時の率直な感想をお聞かせください。
震災直後の4月に帰国し、ゴールデンウィーク明けに被災地である宮城県の荒浜、塩竃、石巻を巡りました。石巻を訪れた1日目は友人を訪ね、2日目には独りで港のほうを歩きました。大破した家々がそのまま残っていて、人は誰もいなくて異様なまでにシーンとしていて、どう表現すればいいのかわからない不思議な世界でした。
後に、ドキュメンタリー作品『friends after 3.11【劇場版】』を発表されていますね。
僕自身はドキュメンタリーの監督ではないので、その当時は震災をテーマに撮ろうとは思いませんでした。しかし直後に起こった、福島の原子力発電所の事故をきっかけに作品を撮ろうと決めたのです。被災して深く心を痛めている方々にマイクを向けることはできませんでしたが、友人になら話を聞けると思い、震災をきっかけにできたいろいろな友人たちに話を聞くというテーマでドキュメンタリー作品を発表しました。冒頭に出てくる津波の映像は僕の姪が撮った生の映像をそのまま使っています。
残された人といなくなった人は、ともに在り続ける

2012年にはチャリティーソング『花は咲く』の作詞も手掛けられていますね。
知人のプロデューサーから「復興応援ソングを作りたい」と打診がありました。しかしながら僕自身は、復興応援ソングと言われてもピンとこない部分がありました。それは、自身が見てきた被災地や、東北の人たちのメンタリティや性質を考えると、“応援する”ということに違和感があったからです。
命が助かった方の背後には、いなくなった家族や友人がたくさんいます。また、命が助かった方の話をお聞きするうちに、急に目の前からいなくなったからといって、いなくなったことにはできないことに気づいたのです。実際に僕自身、亡くなった人から今も大きな影響を受け続けているという事実があります。今はいないけど影響を受け続けている人と、生きているけど全然会っていない友人では何が違うんだろうと考えていくうちに、いなくなった人を無理にいなくなったことにしなくてもいいと思いました。むしろ残った人たちだけではなく、いなくなった人たちも一緒に考えていくことが、本当の復興の力添えになるのかもしれないと思ったのです。そこで、全ての人が“ともに在り続ける”というテーマで作詞しました。
一人ひとりが長い時間をかけて震災に向き合い、未来を良くするアイデアを

最新作である『ラストレター』は、地元をロケ地にされたそうですね。
そうですね、機会があれば自分の郷里で映画を撮りたいと思っていました。以前訪れた石巻で、想像を絶するようなつらい体験をされた方が笑顔でカラッとご自身の体験を話してくださったのですが、「監督、泣ける映画を持ってきてよ。映画館の真っ暗なところでいいから、思う存分泣きたいんです」と口にしたのです。皆さん、普段は気を張って明るく笑っているけど、本当はつらくて苦しい。周囲に泣ける場所がなかったのです。その言葉がずっと心に引っかかっていて、何か映画を撮らなきゃいけないと思っていました。
昔から生死の問題が自身の創作テーマではあるのですが、震災を経て、また新しい生死の在り方を考えるようになりました。その影響は“すぐに、何が、どのように”というよりは、時間をかけて自身に染みてきているような感覚。震災以前と以降では、やはり作品の世界観が違いますね。
震災以前と以降で当時の記憶や経験が反映されているようですが、一般の人は、震災の記憶や思いとどう向き合えばよいと思いますか?
こうして年に一度、当時のことに思いを馳せることはとても大事ですが、みんなが震災の経験を同じように捉えなくてもいいとも思います。それぞれに忘れがたい記憶は異なるでしょうから、それぞれの大切な記憶をシェアしたり、学んだ教訓を未来に生かしたりと、一人ひとりが手分けして考えていけばいいのです。長い時間をかけて、それぞれが考え続け、向き合い続ける。そういうアクションから生まれた発想が、未来の世界を救う気がしています。
ソフトバンクとしても岩井さんと同様に、震災当時からこれまで、さまざまな支援を続け、震災と向き合ってきました。一緒に取り組んでみたいことなどはありますか?
僕は作品を作る立場の人間ですが、立場や肩書やしがらみを抜きにして、ソフトバンクやそのほかの専門的な知識を持った方たちと、いろいろな意見を交わせる場があると良いなと思っています。それぞれの専門の中で震災を振り返り、未来に生かせることもあるはずです。
震災が起こったことで、人と人をつなぐスマートフォンの重要性がとても高まったと思います。ソフトバンクに限らずこれからの未来を発展させていく企業は、この世界をもっともっと良くしたい!というどこか子供のようなピュアな気持ちを持ち続けることが大切だと思っています。
(掲載日:2020年3月10日)
文:山口美智子
編集:都恋堂
撮影:岩田安史